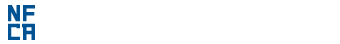プレス情報
2025年9月22日 中建日報 近未来コンクリート研究会 牡蠣殻利用、後添加型流動剤で予備実験 25年度第1回の協議会開く
近未来コンクリート研究会
牡蠣殻利用、後添加型流動剤で予備実験
25年度第1回の協議会開く
近未来コンクリート研究会(十河茂幸代表)による2025年度第1回目のテーマ別協議会が16日、広島市中区で開かれた。協議会には、実会場への出席と全国からのWEB参加を含めて延べ約70人が参加。3協議会合わせて約6時間の長丁場となったが、コンクリートの延命化や脱炭素の研究、施工性改善に向けた議論をさらに深めた。
午前に行われた脱炭素コンクリート技術研究(S)協議会では、広島工業大学の坂本英輔教授が中心となり、コンクリート工学会年次大会2025「低炭素型ポーラスコンクリートの製造方法及び基礎特性に関する実験的研究」の内容が情報共有されたほか、広島県から相談があったという牡蠣殻粉末のコンクリート材料としての利用に関する可能性を議論。これまでにない事例で研究の価値があるとして、まずは予備実験を試みることとした。
また、午後から開かれた「コンクリートの施工性改善技術研究(CⅡ)協議会」では、広島工業大学の竹田宣典教授が主査を務め、施工性改善に適した技術として、打ち継ぎ処理剤などに関する土木学会年次大会の論文調査結果が紹介され、協議会内でも議論。締固めの合理化を目的とした新技術も示された。さらに、後添加型の流動化剤増粘タイプによる施工性改善に関する話題では、予備実験を行うこととし、希望者が参加することになった。
また、コンクリートメンテナンス協会の江良和徳氏を中心に進めている「RC構造物の延命化技術研究(M)協議会」では、冒頭でNEXCO西日本エンジニアリング中国の山本雅行氏による博士論文「塩害環境下にある既設コンクリート構造物の品質評価に関する基礎的研究」に関する講演が行われ、凍結防止剤由来の塩害などについて質疑応答。長崎県端島(軍艦島)での補修技術調査への参加計画なども紹介された。
次回協議会は、12月16日に開催する予定としている。
牡蠣殻利用、後添加型流動剤で予備実験
25年度第1回の協議会開く
近未来コンクリート研究会(十河茂幸代表)による2025年度第1回目のテーマ別協議会が16日、広島市中区で開かれた。協議会には、実会場への出席と全国からのWEB参加を含めて延べ約70人が参加。3協議会合わせて約6時間の長丁場となったが、コンクリートの延命化や脱炭素の研究、施工性改善に向けた議論をさらに深めた。
午前に行われた脱炭素コンクリート技術研究(S)協議会では、広島工業大学の坂本英輔教授が中心となり、コンクリート工学会年次大会2025「低炭素型ポーラスコンクリートの製造方法及び基礎特性に関する実験的研究」の内容が情報共有されたほか、広島県から相談があったという牡蠣殻粉末のコンクリート材料としての利用に関する可能性を議論。これまでにない事例で研究の価値があるとして、まずは予備実験を試みることとした。
また、午後から開かれた「コンクリートの施工性改善技術研究(CⅡ)協議会」では、広島工業大学の竹田宣典教授が主査を務め、施工性改善に適した技術として、打ち継ぎ処理剤などに関する土木学会年次大会の論文調査結果が紹介され、協議会内でも議論。締固めの合理化を目的とした新技術も示された。さらに、後添加型の流動化剤増粘タイプによる施工性改善に関する話題では、予備実験を行うこととし、希望者が参加することになった。
また、コンクリートメンテナンス協会の江良和徳氏を中心に進めている「RC構造物の延命化技術研究(M)協議会」では、冒頭でNEXCO西日本エンジニアリング中国の山本雅行氏による博士論文「塩害環境下にある既設コンクリート構造物の品質評価に関する基礎的研究」に関する講演が行われ、凍結防止剤由来の塩害などについて質疑応答。長崎県端島(軍艦島)での補修技術調査への参加計画なども紹介された。
次回協議会は、12月16日に開催する予定としている。